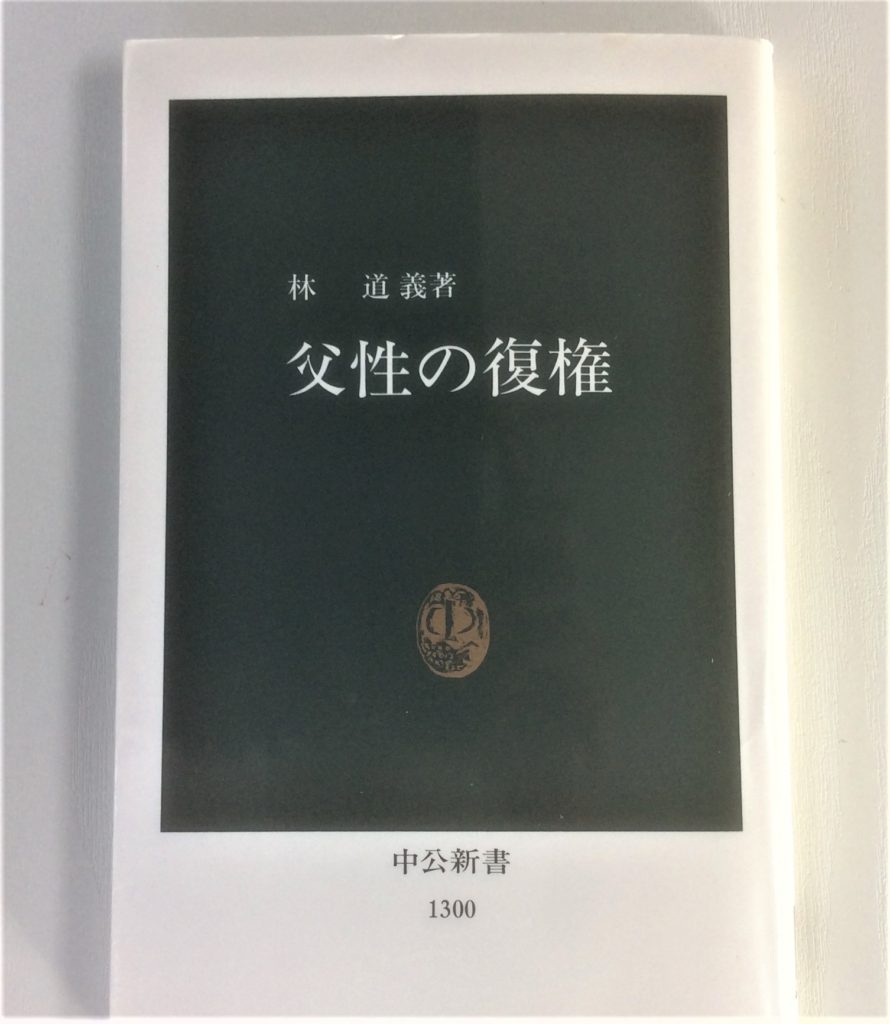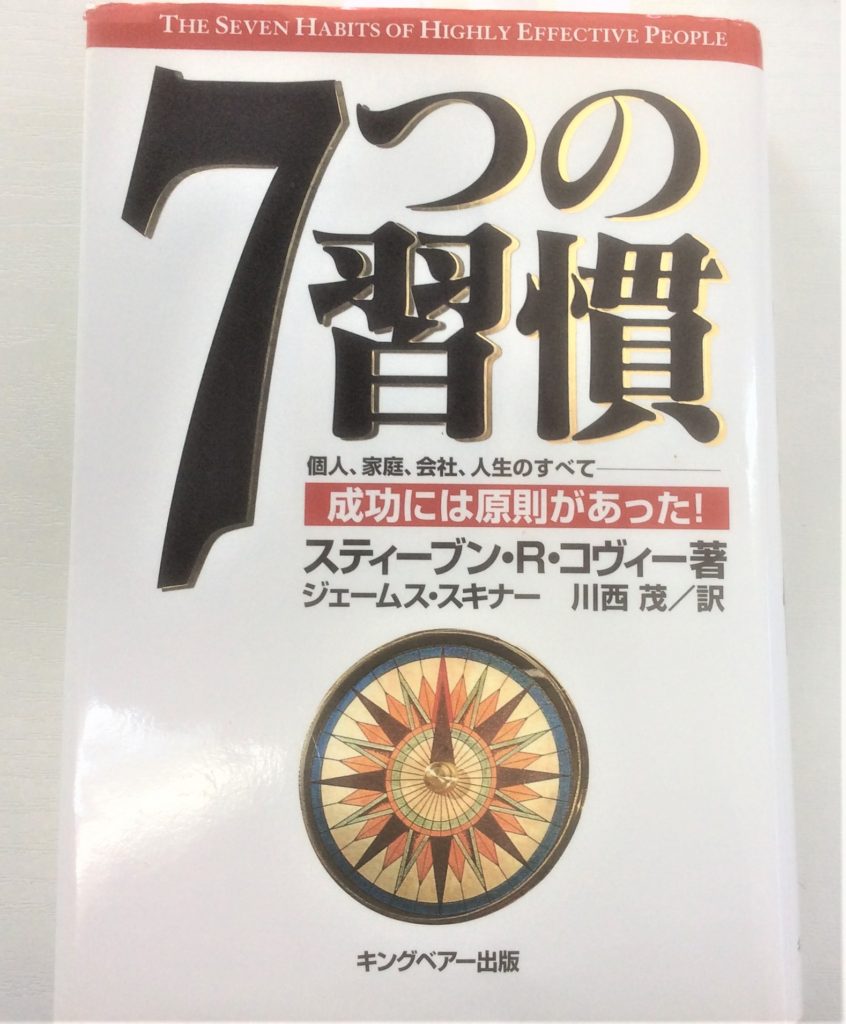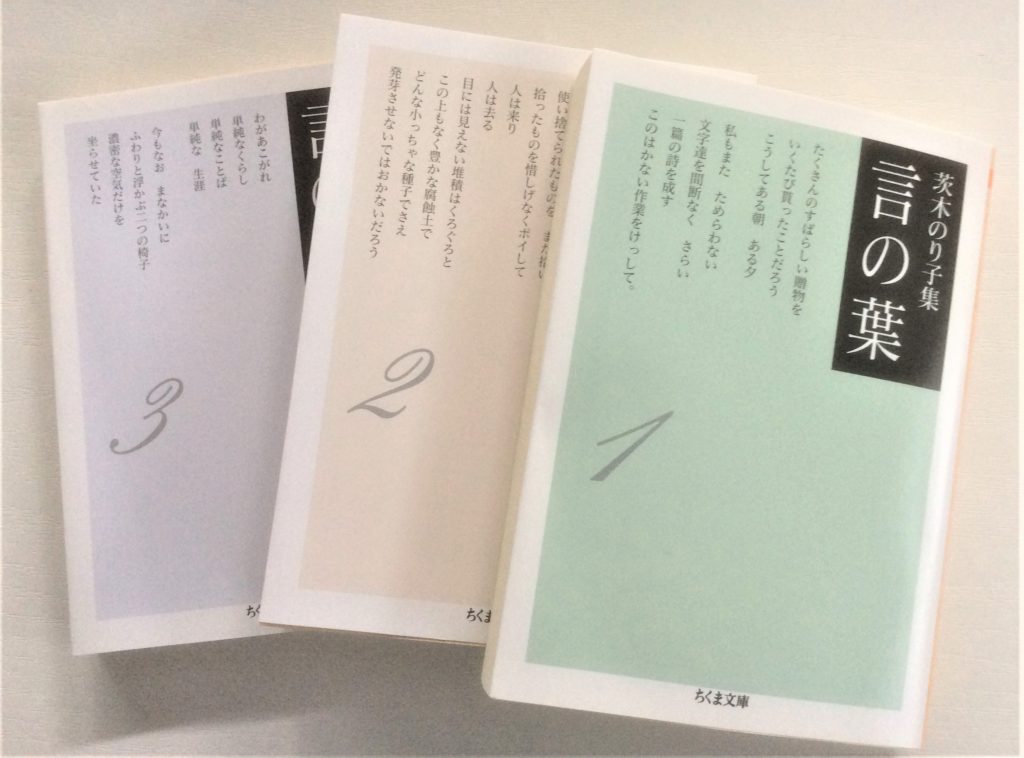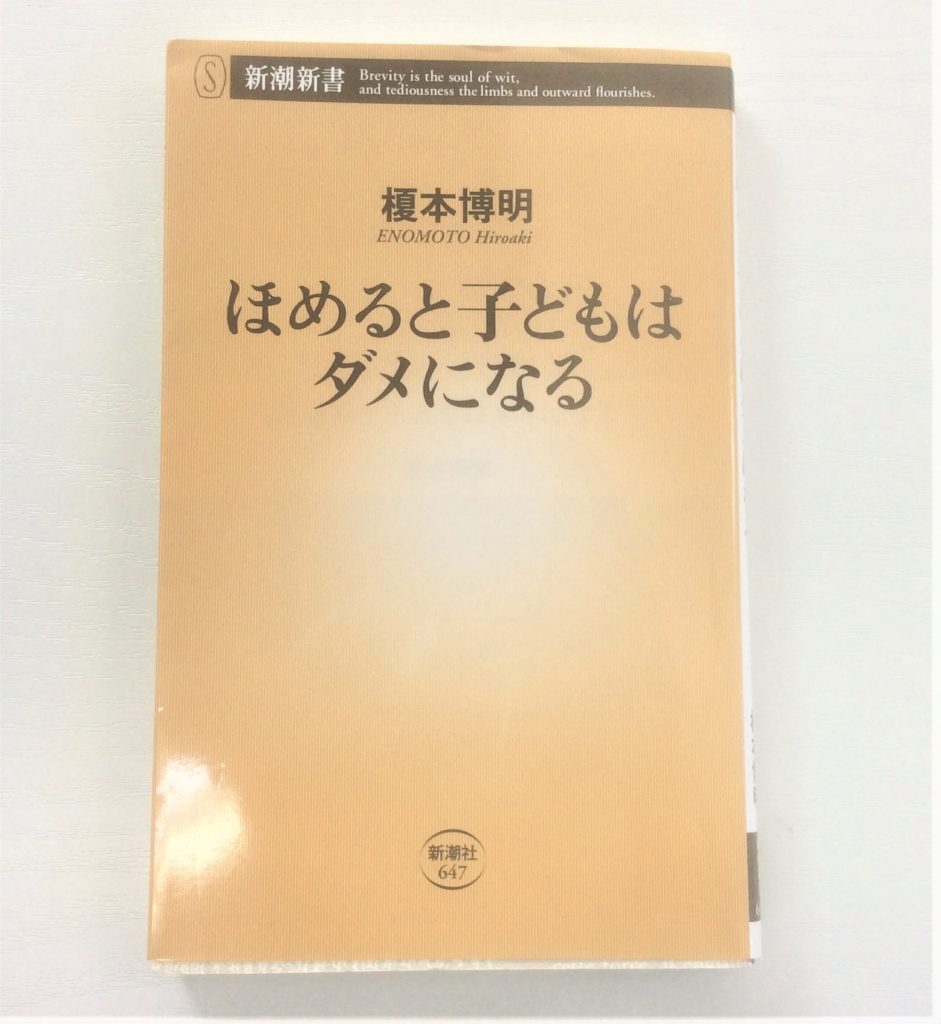新シリーズの「若い先生に向けた内容」の第3弾で、
今回は「父性」について掘り下げていきます。
現在の日本では「行き過ぎた母性教育」が行われており、今後「ほめる思想」に代わって「叱る思想」が必要になると、前回「叱る思想」で書きました。
河合隼雄の言葉を借りれば、「接触をもちつづけてきた母性」といかに「分離」するかの問題に我々は悩んでいます。
その「分離する力」こそが父性であり、家庭や教育現場に「父性」と「母性」のバランスを取り戻さなければなりません。
それでは、我々が取り戻すべき「父性」とは、一体どんなものでしょうか。
今まで私が読んだ様々な教育関連の本に、度々引用されてきた一冊の本があります。
東京女子大学の教授であった林道義が書いた「父性の復権」です。
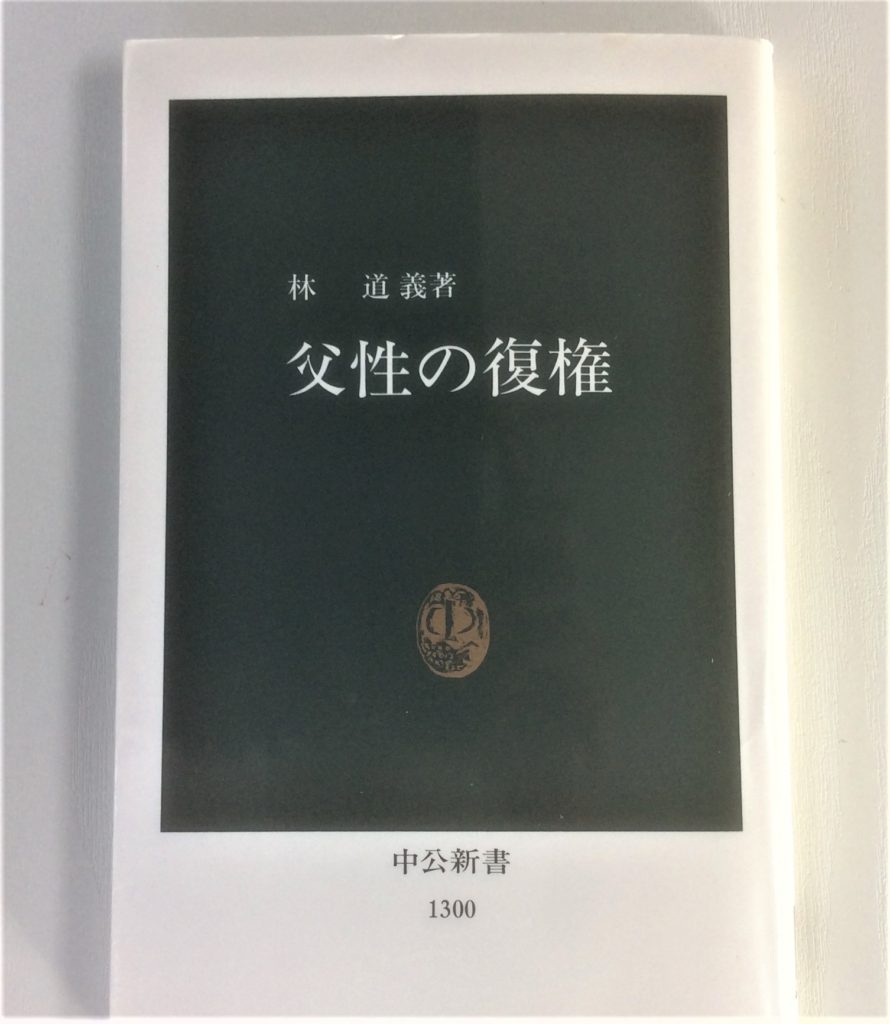
その「父性の復権」において、林は父性についてこう述べています。
原理原則を持っていて、それを具体的場面に適用できるのが父性である
そして父性のない父親に対しては、「友達のような父親」「もの分かりのいい父親」であり、「父親の役割を果たせなくなった父親」と表現しています。
つまり、継承するべき「何ものか」を持たない父親です。
「父親」を「先生」に替えても、そのまま当てはまります。
上下関係のない「友達のような先生」は、先生ではありません。
せいぜい「いい話相手」程度の存在でしょう。
「もの分かりのいい先生」も、然り。
自分の中に守るべき「原理原則」がないから、生徒を「何でも自由」にさせられるのです。
子どもに「合わせる」のではなく、子どもを原理原則に「合わせさせる」のが教育です。
スティーブン・R・コビーは、世界中で3,000万部以上発行された「史上最高のビジネス書」であり「永遠の人間学」と言われる「7つの習慣」を書き遺しました。
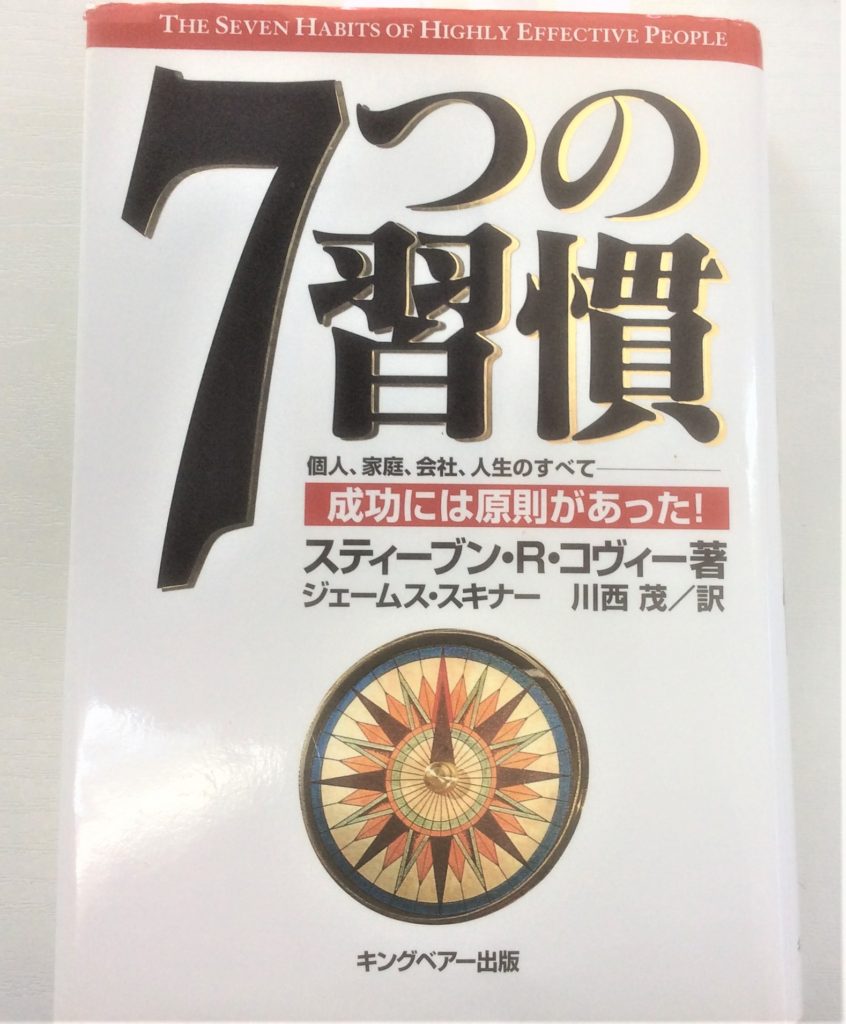
その中でコビーは、長期的に成功する個人や組織、家庭の条件として、「原理原則を守ること」を最重要視しています。
それは地球上どこでも普遍であり、時間を超えて不変であり、
つまりそれは絶対的なものである
そして「原則」の例として、「勇気」「公正さ」「誠実」「貢献」「忍耐」「犠牲」などを挙げています。
現代の我々が嫌いな「忍耐」や「犠牲」が人類の絶対に守るべき原則として紹介されていますが、もちろん間違っているのは「名著」ではなく、我々の感性です。
今の多くの日本人が行っている「父性なき母性教育」とは、要するに「原理原則」を持たない「何でもあり」の「ええじゃないか」です。
我々は、そのような人間を育てていることに、気づかねばなりません。
その「父性なき母性教育」を受けた若者たちは、自分の育てられた通りに、社会のあちこちで「ええじゃないか」を体現しているではありませんか。
詩人 茨木のり子は、「自分の感受性くらい」という有名な詩を書き遺しています。
ぱさぱさに乾いてゆく心を
ひとのせいにはするな
みずから水やりを怠っておいて
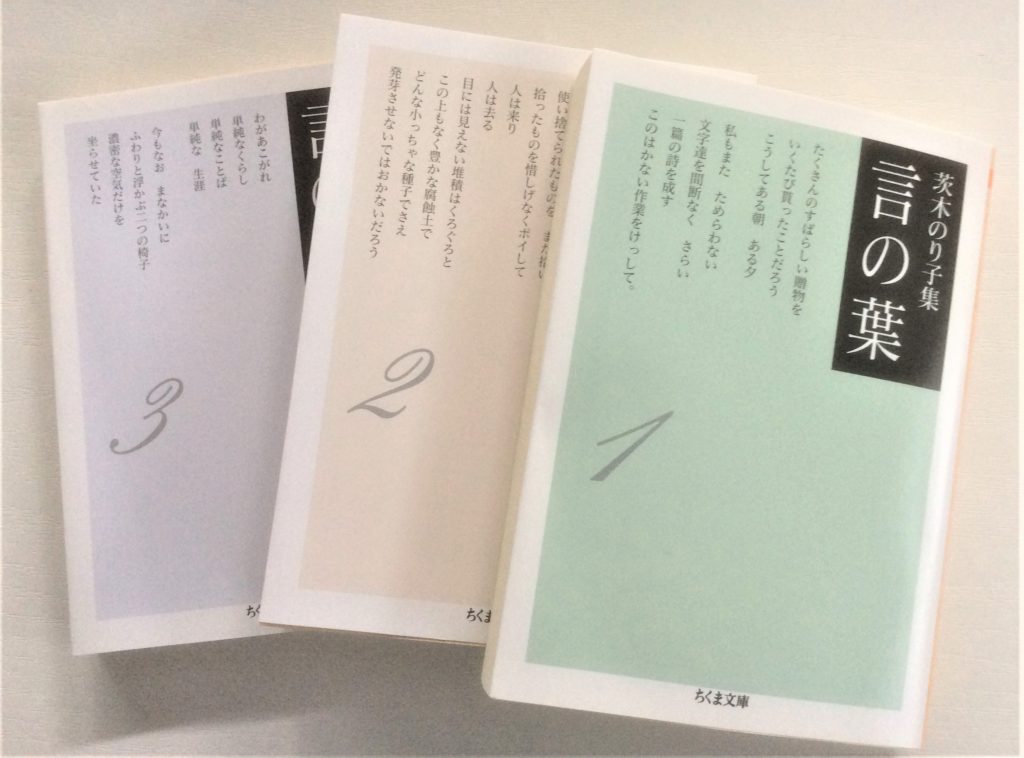
今の躾も何もない、原理原則を持たない子どもたちを見て、何も感じなければ、その人の感性は死んでいます。
「時代がそうだから」
「周りもそうだから」
だから「しょうがない」では、感性の死人です。
詩人は、そんな「不感症」になった私たちを、こう叱りつけます。
自分の感受性くらい
自分で守れ
ばかものよ